 
エピローグ
「千年帝国より、火急の使者が参っております。いかがとりはからいましょうか」
「今は会わぬ。どうせ、『バルディアスの門』のことで文句を言ってきたのだろう。聞いたところで埒もないことだ。放っておけ」
クレティナス王国第一五代国王アスラール三世は、王妃レティシア姫をともなって、宮殿の中庭に広がる庭園にいた。久しぶりに王宮にも降り積もった純白の雪を見つめている。子供のように、冷たい雪を手にとって丸め、重い雪に必死に堪えている針葉樹の枝に投げつけた。
「陛下、直接触られては、お手が」
使者の報告に現われた宰相ウォンテリュリーが慌てて声をあげる。
「いちいち、こんなことぐらいで騒ぐな、ウォンテリュリー。余はそんなに弱くはない。宇宙をこの手につかもうという男だぞ」
「ですが……」
「ウォンテリュリー殿、いいのです。陛下のお好きなようになさってあげてください」
心配そうな視線を向ける老いた宰相に、レティシアが促した。
「レティシア様……」
ため息まじりに呟いて、ウォンテリュリーは無邪気に雪と遊ぶ王の姿を眺めた。
クレティナス国王アスラール三世の美しさは、ガラスのような危うさを伴っていた。偉大なる英雄王、史上最高の名君という呼称に反して、彼の容姿はあまりにもはかない。神神の姿を連想させるものであっても、猛々しい戦神や体力あふれる農神とはかけ離れていた。天才的な才能と大いなる覇気がなかったら、見る者は、彼を妙に白い精気のない人間だと感じたであろう。
アスラールは先天性の血液病だった。青年になるまでは、体内に潜伏し発病することもなかったが、数年前から何回か風邪のような軽い発作を起こしていたのである。彼の病気は、クレティナスの進歩した医学でも治すことのできない、特異なものだった。その事実を知っているのは、レティシアとウォンテリュリーをのぞいて数名しかいない。アスラールに知らせないために、一切の他言を禁じられていたのである。だが、アスラール自身は、自分の命が長くないことに気が付いていた。
「二人とも、そんなに悲しい目をするな。余は不死身だ。この銀河の戦乱を終わらせるまでは、決して、死ぬことはないのだ。見ているがいい。いずれ、余の足元に、銀河皇帝も銀河教皇も平れ伏させてやるからな」
「アスラール様……」
アスラールは笑った。自分の運命など意にも介さない、大きな声である。
笑いながら、彼の視線は沈みかけた夕日の向こうに浮かぶ一番星に向けられていた。
「人の生命は短い……その短い生命のなかを、みな一生懸命生きている。余もみならいものだ」
雪に反射する夕日を浴びて、アスラールのアイスブルーの瞳は輝きを増した。
表情に笑みが浮かび、何かを楽しそうに考えている。
「……ようやく、戦える。あの大いなる巨人、グレイザーが創った千年帝国と戦うときが、ついに来たのだ」
「陛下!」
老宰相が声をあげる。
「止めても無駄だ、ウォンテリュリー。余は行くぞ。この銀河を手に入れるために。行って新しい時代を創るのだ」
銀河の戦乱は二○○年目を迎えて、急速に展開を始めた。要因の一つには、アルフリート・クラインの戦いもあげられたが、大部分は、英雄王アスラールの覇気に求めることができた。銀河の弱小国クレティナスを、わずか一○年にして、人類の覇権をかけて戦える強国に成長させ、次には、銀河の支配者、千年帝国と存在と未来をかけた戦いを繰り広げようとしている。彼と人類の夢である銀河の統一は、遠い未来のことではなかった。
しかし……
レティシアの脳裏を、赤い髪の青年の姿がよぎった。
「あなたは、いったい何を考えているの?何のために戦っているの?」
幾多の戦いに参加し、無数の敵を破ってきた若き英雄。彼の本心が、このクレティナスを滅ぼすことであることを彼女は知らない。そして、いつの日か、彼女の最愛の夫アスラールを滅ぼすことを。
|
 |
  |
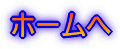
|

